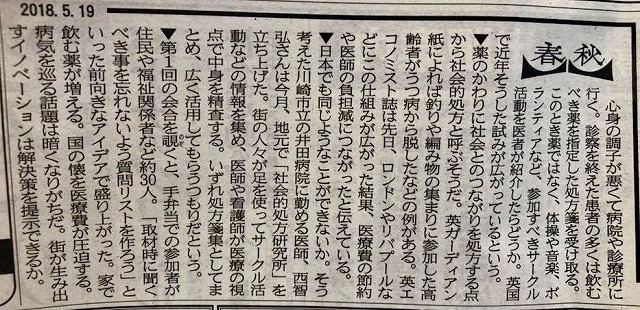NURSE FES TOKYO 2018 ご報告
2018年5月27日(日)・28日(月)に渋谷で開催されました日本最大級のナース限定イベント「NURSE FES
TOKYO 2018」に、当協会も参加させていただきました。

両日合わせて6000人近くの看護学生さん・看護師の皆様が来られる中、 当日はセッションエリア内で
「ゆだねるヨガ」 として、寝るだけのリストラティブヨガが気軽に体験できるスペースを提供いたしました。

体が固いから・・・
体力がないので・・・
ヨガクラスまで足を運ぶ気力がない・・・ などとおっしゃる看護師の皆さまに、リストラティブヨガという選択肢をご提案。
やはりpractice based medicineであるヨガ、百聞は一見?いや一体験にしかずでした。
そして、さすが看護師さんです。
「これならどんな患者さんにでもできますね」 「病院なら枕もタオルケットも砂嚢もたくさんあるから、入院中のベッドの上でもできますね」 「付き添いの家族の方のリフレッシュにもなるかも」 「家族と一緒に無理なく行えることがあったら患者さんも嬉しいでしょうし、ご家族の喜びにもつながりま すね」
などなど、ご自身の職場でどう活かしていけるかを早速考えていらっしゃいました。
まずは自分を大切にしてみる、その上でだからこそ、自然に周りにいる方を大切に考えていくことができる。 ! ほんの短い時間の交流ではありましたが、来訪してくださった方お一人お一人からそのことを改めて教えて いただく機会となりました。
改めまして、今回このような機会をくださりました
株式会社エス・エム・エスキャリア NURSE FES TOKYO 2018事務局の皆様、 そしてご縁をおつなぎくださりました当協会会員の吉井久美様に御礼申し上げます。 ありがとうございました。
(松原 昌代)
【ヨガセラピストの本棚】第一感 (原題:Blink) マルコム・グラッドウェル
アメリカのヨガセラピストは時に全くヨガに関係のなさそうな本を教材書籍とするが、本書もその例外ではありません。
世間には第六感という言葉はあるが、理屈以前のひらめきである第一感(Blink) についての本です。理屈以前の話であるため、理屈以前では説明しにくいことなのですが、マルコム氏はこの概念をパブリックなメディア(ニューヨーカー)で堂々と問うたジャーナリストとして注目を集めました。本書は謙虚に「理屈以前」の事例を検討しながら説明を試みています。
一気に結論に達する脳の働きをAdavtive Unconciousness (適応性無意識)といいますが、現代の心理学で注目されている研究分野の一つです。これは、フロイトの精神分析でいう無意識とは別物です。フロイトのそれが、意識すると心を乱すような欲望や記憶、空想をしまっておく場所であるのに対し、適応性無意識は強力なコンピューターのようなもので、状況判断や、危険告知、目標設定、行動の喚起などを瞬時に行うものです。
ER(救急救命室)のモデルとなった、シカゴのクック・カウンティ病院の事例が非常に示唆に富んでいるのでご紹介します。
クックカウンティ病院は全米で初めて、ゴールドマンの心疾患リスク評価方を採用しました。1996年、ブレンダン・ライリー氏が医局長に就任してから、大改革が行われたのです。それは、胸の痛みを訴えて救急室に運ばれてくる患者の診察方法を根本的に変えようというものでした。
ライリーの指摘は、情報集めに熱中しすぎると、データに溺れてしまう。情報が増えるほど、判断の正確さに対する自信は、高くなる一方、皮肉なもので正確な判断ができなくなるということでした。頭の中にある詰め込み式の計算式に情報を追加しすぎ、ますます計算式が複雑になってしまうからです。当時のクック・カウンティ病院を始め、多くの救急病院での診察方法がそうでした。
それに大きなメスを入れたのがライリーだったのです。
クック・カウンティ病院の実験の教訓は「何かを判断する際、情報は多いほど適切な判断をくだせると、皆当たり前のように思い込んでいる」ということです。
それは、ヨガセラピーについても同じことなのです。私たちは、セラピーを行うにあたり、同じ様なことをしてしまう可能性が大いにあるのです。
生徒さんの症状は多様であり、ヨガセラピーは症状そのものを解決させるものではないということを忘れてはなりません。私たちヨガセラピストはそれを治療したり直したりする立場にあるわけではないのです。
むしろ、私たちは目の前の人を、変えたり直したりすることなく、ありのままを受け入れることから始めなくてはなりません。その上で、何をするのか、それはとてもシンプルなことです。
(2)刺激を遮ること
(3)緊張を解くこと
倫理講座や認定説明会で説明していることですが、ヨガセラピーの究極のゴールはDeep Sleep, Less Stress です。それを妨げている、呼吸の乱れ、刺激過多、過緊張に対してヨガセラピーはシンプルに強みを発揮します。姿勢を良くしてください、ではなく、胸の緊張を緩めましょう、というアプローチです。
本書では他にも次の様なことに言及しています。
第一感といえども、曇ることがあります。
むしろこの、第一感の曇りがトラブルを引き起こすことがあります。例えば、私たちは興奮すると、人の心が読めなくなったり、時間がないと、先入観に引きずられたりするのです。これはマインドブラインドネスと言われたりします。慢性的なものは病気(自閉症など)とされますが、わかってきているのは、これが一時的に現れ、正常だと言われている人がひどく間違った結論を導き出すこともあるということです。
脳の一部に損傷があり、知識と行動のつながりが断たれてしまうと、自分の行動の結果をきちんと説明できるが、その通りに行動できない、という事態が起こります。しかしこれは、第一感の曇りによって、瞬間的に誰にでも起こりうるかもしれないのです。
著者のメッセージは、綿密で時間のかかる、理性的な分析と同じぐらい、瞬時のひらめきには大きな意味がある。そのことを認めることで、自分自身をもっとよく理解できるのではないだろうか、ということでしたが、私たちヨガセラピストが本書から学ぶこともまた、いわゆる第六感やチャクラ、というものだけではなく、もっと私たちが自然にもつ「なんとなく」という感覚を素直に信じてみませんか、ということではないでしょうか。
繰り返しになりますが、その意味を理解することで、私たちは目の前のことを変えたり直したりすることなく、ありのままを受け入れることができるのではないでしょうか。
ヨガセラピーの認定講座を制定するときに、ヨガ業界以外の方から多くご指摘を受けたのは、認定という高みを作ることによって、簡単なことをわざわざ難しく説明するセラピストが増えるのが心配だ、ということでした。ヨガの良さはシンプルなことなのだから、学びを深め、認定を受けたセラピスト達は、より物事をシンプルにし、相手の立場に立って分かりやすく説明できるようでありたいと考えます。
************
なお、クックカウンティ病院の改革についてはJAMAで
「Impact of a Clinical Decision Rule on Hospital Triage of Patients With Suspected Acute Cardiac Ischemia in the Emergency Department」というレポート(英語)としてまとめられています。興味のある方はご覧になってみてください。
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/195118
グリーフケアとヨガ勉強会 開催いたしました。
【分科会勉強会報告】グリーフケアとヨガ
5月19日(土)開催
参加人数:4名
開催場所:スタジオ My Luggage(横浜)

グリーフケア勉強会が開催されました。
ご経験者の方々、医療従事者の方々にご参加いただきそれぞれの立場からの経験されたお
話・ご意見を頂きました。
医療現場で実際に行われているグリーフケアの取り組みをお聞きすることもできました。
3ヶ月・6ヵ月たつ頃ご家族に手紙や電話で連絡を取りご様子を伺ったり、家族会をつくり
グループセッションをしたりといくつかの方法で取り組んでいらっしゃる中での、難しさ
やお悩みをシェアして頂きました。
終末期からの取り組みも必要ではないかとのご意見も頂きました。


『言葉は薬にも毒にもなる』
声をかける難しさも皆さんが感じていることでした。
励ましではなく、優しい傾聴が必要である難しさです。
私もそう思うからです。痛みが走りました。
実際心的反応・肉体的反応は資料に記載した症状が次々と現れ、治まったとしてもそれは
突然また現れるのです。それだけ簡単ではないという事です。
また、故人との関わり方やバックボーン、家族関係によってもとらえ方も様々です。
実際に人に言われる事により思ってもみなかった感情に悩んでしまったとのご経験もお話
頂きました。
現れてくる心的反応・肉体的反応も様々であり順序よく現れるものでも、順番通りに無く
なるものでもありません。
今回の勉強会では実際にヨガにできることの実践的なところまでは時間が足りませんでし
た。それだけお話が尽きない大きな問題であるのがグリーフケアなのだと再確認致しまし
た。
そしてお話頂いた実情や経験者の方々の貴重なお話はこれからのグリーフケアの取り組み
にとても大きな力となることと思います。
グリーフケアの存在をまずは一人でも多くの方に知って頂くこと!
他人事と思いがちなこの問題を誰でも起こり得る事と認識して頂き、誰かに寄り添えるす
べを知り、自身がそうなった時自身が抜け出せるすべを知っていただくためにはメディア
に取り上げてもらえるといいのにというお話が出ました。
NHKのような重たい話では見てもらえないので、池上彰さんに取り上げてもらえると見ても
らえ知ってもらえるのではないかと、メディアの大きな力も借りていければと新たな目標
も出てきました。
社会に必要なグリーフケアをヨガと共に寄り添える日は必ず来ると思います。
そうなれるよう今後ともよろしくお願いいたします。
グリーフケア勉強会にご参加いただきました皆様に心より感謝申し上げます。
グリーフケアとヨガ座長 杉島小百合
「NURSE FES TOKYO 2018」に参加します。
看護師の皆さまにフェスのお知らせです。
来る5月27日(日)&28日(月)
渋谷で開催されます日本最大級のナース限定イベント「NURSE FES TOKYO 2018」に、日本ヨガメディカル協会がセッションエリアで参加します。
協会のパンフレットや関連書籍をご用意し、寝るだけのリストラティブヨガが気軽に体験できる
スペースもご用意しております。
よろしければ是非とも足をお運びください。
<5月28日(月)>
session 3(Bエリア)|15:00~18:30
フェスの詳細、イベントスケジュールは「NURSE FES TOKYO 2018」でご確認ください。
協会一同、皆さまのお越しをお待ちしております。
社会的処方箋
一般会員 秦絵理子さんからの投稿をご紹介いたします。
イギリスで、薬の処方箋の代わりに、体操や音楽、ボランティアなど、参加すべきサークル活動を医師が紹介したらどうかという試みが広がっているそうです。社会的処方箋というそうです。釣りや編み物のサークルに参加した高齢者がうつ病から脱したという例があるそうです。
川崎市立の井田病院に勤める医師西智弘さんが、「社会的処方箋研究所」を立ち上げたとのこと。
【2018年5月19日の日経新聞の記事】