「看護とヨガ」LINEオープンチャットのご案内

昨日、新型コロナウイルスへの対応を続ける医療従事者の皆様へ感謝の気持ちを表して、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」が東京の空を鮮やかに飛行しました。
日本ヨガメディカル協会でも何か、医療従事者の方への恩返しになるようなことをということで、看護師であり当協会の医療普及部でもある松原昌代先生より、以下のご提案です。
================================================
2020年4月より、協会ではヨガセラピーに興味をお持ちの看護師さんたちが思いや気持ちをシェアできる場として、また経験を共有したり質問できる場として、毎週土曜日にzoomを用いてのオンライン会議を開催してまいりました。
ここまで1ヶ月が経過しましたが、交代制の勤務につかれている方も多いため、決まった日時に希望者全員が交流を持つことはやはり難しいという結論に至りました。
そこで、みなさんそれぞれの可能な時間にアクセスできるよう「看護とヨガ分科会」座長の松原がオープンチャットを開設いたしました。
まずは当協会に関わる看護師さんたちにご参加いただき、自由に気軽におしゃべりをする中で志を共有したりお互いに学び合うための場を熟成させていければと思っております。
またそこから多くの看護師さんたちに、看護と親和性の高いヨガセラピーの存在を知っていってもらえるきっかけを作っていきたいと思います。
仲間を見つけたい、気分転換がしたい、モチベーションにつながるような刺激やヒントがほしい、他の人がどんな活動をしているのか知りたい、自分の思いや経験をシェアする場がほしい、疑問に思ったことを話し合いたい、自分の活動を広げていきたい、違う視点から物事を考察したいなどの思いをお持ちの、様々な立場の看護師さんのご参加をお待ちしております。
<参加条件>
ヨガやヨガセラピーに興味をお持ちの看護師
・ヨガやヨガセラピーの経験は問いません
・看護師経験は問いません
・当協会会員を中心とした運営となりますが、非会員の方の参加も可能ですのでぜひ周りの看護師さんにもご紹介ください。
<オープンチャットの安全性について>
・オープンチャットはLINEをベースにした誰でも参加できるグループを作成しチャットできる機能ですが、今回は管理者の承認を必要とする安全な場を提供いたします。
・不適切な発言をするなどその人物の参加により場の安全が保たれないと判断された場合には、管理者により強制退室処理(再入室不可)します。
・管理者にも参加者にも、LINE ID・アカウント名・本名などの個人情報が知られることはありません。ユーザー名とアイコン画像を別に設定して参加していただくと、さらに安全性を高めることができます。
・途中から参加しても過去のトークをさかのぼって閲覧することができます。
参加を希望される方は下記よりお申し込みください。
「yoga nurse」
《 松原昌代 》
~開催報告~ シニアヨガ指導者・オンライン座談会
2020年5月20日・23日・26日に、シニアヨガ指導者養成講座・履修生の方々の オンライン座談会を開催いたしました。18名のご参加を頂き、和やかで有意義な会になりました。 「あれから、どうしてた~?」これだけで何時間でも会話は続きそうでしたが、やはり話題の中心 はコロナでした。 活動が大幅に制限され、困った、不安になった(進行形も含めて)事など… 頂いたお話をご紹介いたします。
1、困ったこと
・シニアの生徒さん達と、繋がる方法が無い
・携帯電話はお持ちでも、メールやラインを使う方は少なく、オンラインは無理 ・特に、一人暮らしの方は電話をかけるが、詐欺防止から事前に先方の電話機に 登録してある電話番号以外は拒否される 《解決・改善策と》
・最初の参加同意書の重要性を再確認した 住所、連絡先、メルアド、又はご家族の連絡先までを記載して頂く 既に頂いている方々の見直しをする (第2波に備えて)
・はがき、手紙で安否を問う (紙でのマニュアルなどを作って郵送もあり)
・再開したら、可能な皆さんには ZOOM をインストールして頂く(第2波に備えて)
2.不安になったこと
・生徒の皆さんが、元気で怪我無く暮らしているだろうか?
・自分が感染源になっていないか?なってしまわないか?
・自粛解除になった時に、生徒さん達が戻ってくれるだろうか?
・マスク着用しての、ヨガはどうなんだろう????
・これからは、オンラインヨガの時代になるのだろうか?
・マスク着用で、呼吸が思うようにいかないのなら、オンラインのほうがのびのびと ヨガができて、プライベートなどはオンラインも導入よいのでは?
・聴力の弱い方へは、聴こえる方の耳に近いすぐ近くでヨガをして頂き、やや大きめの声で お伝えしていたが、これからはフェイスガードを使えば今まで通りで良いのか?
・マスクだけでなく、フェイスガードも必要か?
・クラスの参加費は、当日現金で頂いていたが、今後はどうしたらよいのか?
・コロナとは関係ないが、ヨガ指導者は《孤独》だなぁといつも思うので、皆さんの話を聞 くと、皆も同じで悩んでいるんだとわかり安心するし、元気が出る
《解決・改善策》
・自分のクラスの再開については、協会のガイドラインを参考に、自分が納得して自信を もって再開できる時に行う
・ヨガの再開については、クラスを持つ各自治体により方法は様々なのでそれに対応する ・マスク・フェイスガード等は、まずは大袈裟かと思うくらいの細心の注意をして行い 体験してみて不必要と思う部分は除き、必要な所は強化して行う
・オンラインの利点もあり、シニアに限らず小さい子供をもつお母さんや、帰宅の遅い方な ど、需要は増えるだろうから、少しづつでも取り入れて行くのが良い(第2波に備えて)
・既にオンラインを活用して「北海道の祖母・叔母とヨガしています」との温かい話も
・オンライン決済に関しては、ここもシニアはあまり積極的に取り入れそうにないので 毎回支払ではなく、ある程度まとめた回数券やチケット制にするなど替えてみる
・孤独な指導者の情報交換の場として、オンライン座談会を今後も行ってほしい
以上、要約させて頂きました。
皆さんの心のうちは同じで、それぞれの話に大きく、強く頷いておられました。
「皆もそうなんだ!」とホットする思いは、コロナ疲れを和らげたのではないでしょうか。
違いがあったのは《自粛ぶり?》で、これはかなり地域差を感じました。 比較的のどかな地域の方は、緊急事態宣言に沿った生活をしつつも、誰にも会わずに歩ける 野山はすぐそこにあり、運動不足どころか健康的にほぼ変わらない生活だったそうです。 また、大阪在住の方は「大阪は第2の都市と言われ、大都市だぞ!」と思っていたけれど ニュースで東京のもの凄い状況をみたら、大阪はまだのんびりしていて、東京とは大違い。 第1と第2の差がめっちや大きいと感じました…」と仰っていました。 長野からの参加者様は「こちらもみなさんマスクはしていますが、比較的ゆったりしていて 観光客が来られないのが残念です。自粛疲れの癒しになればと、自然がいっぱいの写真を Facebook に載せていますよ」とのお言葉でした
皆様が、それぞれの地域で、今出来る事をしっかりやられている事は素晴らしいです。 大きな力を頂きました。
自粛が解けた今、ここから色々な事が、物が変わって行くでしょう。 シニアヨガもこの流れに上手に乗って、皆で!より良い方向に進んでいきましょう! また、ご一緒に笑って語り合える日が、今から待ち遠しいです。 ご参加くださいました皆様、会えて嬉しかったです! ありがとうございました。 皆様のおかげで、パワーと笑顔の溢れる会になりました事、心より感謝申し上げます。
最後になりましたが、この会の企画をご快諾下さいました岡部先生、メール発信等お力添え 頂きました石井先生、ありがとうございました。
講師 伊藤典子 2020・5・27
ヨガクラスの安全な開催における対応ガイドライン(COVID-19) Ver.1
本ガイドラインの目的
緊急事態宣言は一旦解除となりましたが、今後も油断することなく一人一人が予防を心がけながら第二波に備え生活することが求められます。一方で、宣言の解除を受け、ヨガクラスの再開を検討される方も増えてくることが十分に予想されます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、そしてヨガクラスを開催する主催者、指導者、そして参加者の生命と健康を守るために必要な予防対応指針、そして発生時の具体的な対応に関するガイドラインを作成いたしました。
主催者の責任のもとに判断すべき項目もありますが、対応の不備により事態の悪化が発覚した場合、ヨガ業界全体への活動が自粛要請される可能性は十分にあります。また、感染が起こった場合、参加者のプライバシーや 個人情報を含む生活への影響を最小限とするための配慮も必要となります。ヨガクラスを提供されるすべての皆様に、万全の体制での開催を心掛けていただきますようお願い申し上げます。
一方で、ストレス状況下、呼吸を整え、体を適度に動かし、自分自身と静かに向き合うヨガの役割が見直されてきています。安全や安心が希薄になるような世相の中ですが、ヨガのクラスと同様に安全は制度だけでは守れません。一人一人が自分を大切に守ること、そして自分のことと同じように、他人やコミュニティを大切にしたマナーやエチケットを心がけること、ヨガの指導者が伝えられる安全対策は、自他への慈悲であることを考えると、対面のクラスのみならずオンラインのクラスの可能性も大きく広がっていくと考えています。クラスの開催も一気にではなく、安全を確かめながら、徐々に徐々に行動範囲を広げていきましょう。
そして何より、これまで人類が経験したことのない脅威の最前線で、自分自身やご家族の生命が危険にさらされるような過酷な状況下で献身的な努力をされている医療従事者の方々、そして医療をはじめ、国民の健康と生活を支えてくださっている多くの関係者の皆様に、最大限の敬意と感謝を表します。
2020年5月26日 一般社団法人日本ヨガメディカル協会
代表理事 岡部 朋子
ガイドライン ver. 1 は下記より表示・ダウンロードできます。
https://yoga-medical.box.com/v/covid-19-guideline1
リンクにうまく飛べない場合は、リンクのアドレスのコピー & お使いのブラウザへのペーストをお試しください。
また、手洗いの徹底に際しては、手洗い場所に具体的な方法の例示が必要です。下記、サラヤ株式会社様の「衛生的手洗い」のページをご紹介させていただきます。ページの下の方に印刷可能なイラストがあります。
https://pro.saraya.com/pro-tearai/education/index.html
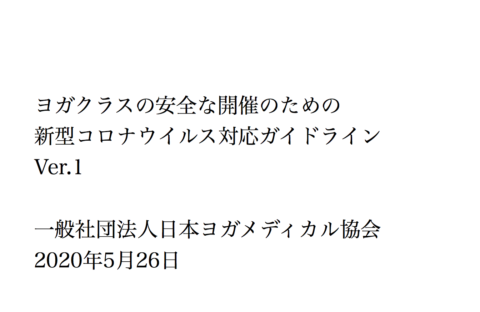
正当にこわがる

「正しくおそれる」表題とは少し異なるこの言葉の方が、みなさんは聞き慣れているかもしれません。
震災以後、また最近の感染症に関連して「科学的な知見を拠り所にしておそれるべきことをおそれ、そうでないことは必要以上におそれないようにしましょう」という意味合いで使われているこの言葉ですが、物理学者・随筆家の寺田寅彦さんの言葉の引用とされることが多いものの、実際にそこに書かれているのは、実は表題の「正当にこわがる」という言葉です。
今浅間からおりて来たらしい学生をつかまえて駅員が爆発当時の模様を聞き取っていた。(略)「なになんでもないですよ、大丈夫ですよ」と学生がさも請け合ったように言ったのに対して、駅員は急におごそかな表情をして、静かに首を左右にふりながら「いや、そうでないです、そうでないです。――いやどうもありがとう」と言いながら何か書き留めていた手帳をかくしに収めた。
ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしいことだと思われた。
寺田寅彦「小爆発二件」より
駅員が示した「おごそか」な表情とありますが、おごそかとは威儀正しい様子のことであり、恐れ(=恐がる)というよりも、畏れ(=畏敬の念)を表している感じがします。そして「正しく」ではなく「正当に」という言葉により、それが事実か否か・合っているか間違っているかというよりは、自然を畏れることは道理にかなっているということを表しているようにも感じられます。
このことについて作家の佐伯一麦さんは「浅間山の爆発についての随筆の中での寅彦は、『正当にこわがることはなかなかむつかしいことだと思われた』と記している。正しく、ではなく正当に、です。科学者たちの言うニュアンスとは正反対のように私には思えます」と述べていますが、みなさんはどう感じられますか?
寺田寅彦さんのいうように、私たちは意図せず「こわがらな過ぎたりこわがり過ぎたり」します。またそれはどちらか片方に固定されるものではなく、自身の状態やそのとき置かれた状況や立場により揺れ動くものです。そして揺れ動いているからこそ、その両方を大切にすることもできるのではないでしょうか。
「正しくおそれて」今それぞれができることに尽力しながらも「正当にこわがっている」今の自分に気づきそれをまるごと受け入れる。それは改めて自分を大切にするための大きな一歩になるでしょう。そしてそこにまたヨガがお手伝いできることがあるのかもしれません。
(松原 昌代)
不安に対処するための5カ条「APPLE」
APPLEとは、不安障害に取り組むイギリスの支援団体であるAnxiety UKが提唱する不安への対処法です。下記の頭文字からなります。
Acknowledge(認める)、Pause(小休止)、Pull back(一歩下がる)、Let go(受け流す)、Explore(探索する)
- Acknowledge(認める):不安を感じたら感じている自分に気づき、不安そのものを認める。
- Pause(小休止): 反応する前に、気づきそのものを観察し、止まって深呼吸。
- Pull back(一歩下がる):不安な感情を客観視する。また始まったと自分に言い聞かせる。答えは出ないことを思い出し、自分が考えていることイコール事実ではないこと、自分が考えていることに責任(ねばならない)を持つ必要もないことを思い出そう。
- Let go(受け流す):不安や感情はそのうち過ぎ去るものだから、流れて行くのを待つ。雲や泡になって流れ去っていくところを想像するのもいい。
- Explore(探索):今に目を向ける。ぜなら今まさにこの時、この瞬間、自分の呼吸、息をする自分の感覚を意識する。地に足がついている感覚を思い出し、たった今自分が見聞きしているもの、触っているもの、香りに意識を向けてみよう(マインドフルネス)
これらはすべてヨガへの取り組みを通じ、行なっていることですね。不安への対処も他のスキル同様、練習を続けることで、上達します。このような時期だからこそ、試してみる価値はありそうです。
(文責:岡部 朋子)
出典:”Coronavirus: How to protect your mental health”